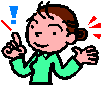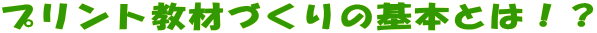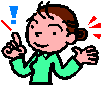|
FD教材シリーズを使い続けている横山先生。
問題づくりに自信があるわけではないが、問題づくりに1つの「法則」というか「ルール」ができあがっているようなので、少し、教えていただきました。
 |
- 単元別に問題を抽出する。⇒1単元、30問程度を抽出する。
- 抽出した問題をプリントの目的にあわせて問題を分類。⇒「観点別」「解答形式別」に分類。
- さらに、分類した問題を解答形式順「選択、整序、空所補充、記述」の順番に並べ替える。
⇒たとえば正答率の高いと予測される問題から順番に並べ替えると、採点・評価の際、生徒個々の理解不足をチェックできる。
- ワープロソフトでレイアウトを整える。
|
 |
Q:まず、「単元別に30問も問題を取り出す」ということですが、どうやって問題を準備するの? |
 |
A:単元別に1つのファイルから構成されていますから、とっても便利ですね。FD教材シリーズだけではちょっと問題数が足りませんので、自作の問題とあわせて使っています。
そのくらい、集めておかないと「教えてないコト」も問題に出ていたりするから。 |
 |
Q:「抽出した問題をプリントの目的にあわせて問題を分類。」ってどういうこと? |
 |
A:たとえば、定期テストを作るときって「採点」することも考えて問題を作ろうとするから、「エンマ帳」につけやすいように、私は観点別にも問題を分類してフォルダーを作って問題を貯めていってます。時間かかるけどね。
でも、記述問題と選択問題の出題のバランスが整わないと、テストの意味がなくなるから「解答形式」には気を使っています。
私の場合は、簡単な問題から難易度の高い問題へというパターンで問題を並べています。たとえば、「選択、整序、空所補充、記述」という順番で。
|
 |
Q:じゃあ、小テストをパーッと準備するとき、便利だよね。 |
 |
A:私はEXCELでオリジナル問題データベースみたいなのを作って管理してるよ。単元名や設問形式なんかでも検索ができるから。複数学年を担当したときでも大丈夫だし。毎年使えるから・・・
|
 |
Q:学校の先生って「一太郎」のほうが使いやすいんじゃないの? |
 |
A:うん。私の学校も「一太郎」だからね。
でも、個人でみんなPC、持ってるからWordだってそこそこは使うよ。
文字をばーって打つくらいで、レイアウトを整えたり・・・っていうのはちょっと難しいみたいだけど。
私もそうだけど、要するに「使う」っていうレベルなんだけどね。「使いこなす」っていうのは、とても、とても・・・(笑) |
|